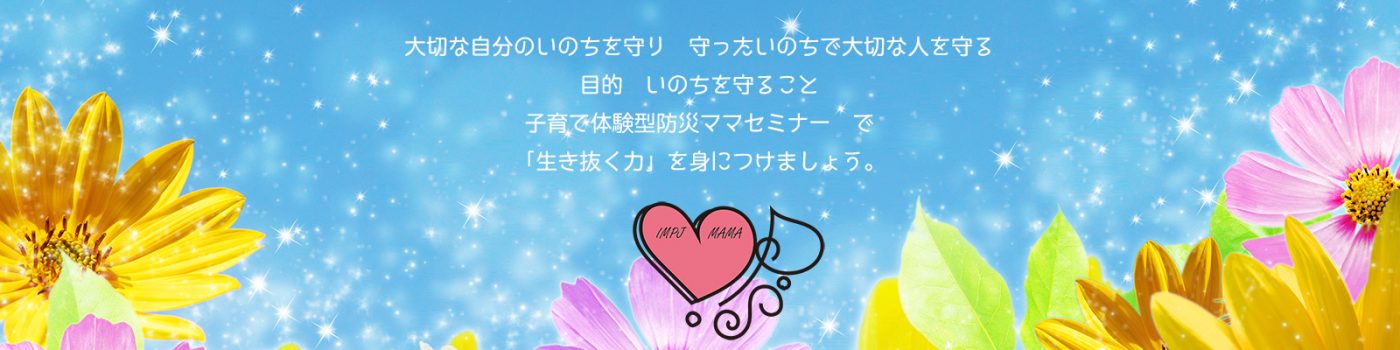靴選びのポイント
いくつか、災害時に特に重視すべき点があります。
天候・路面状況を想定して
那須町では雨・冷え・急な地形変化なども想定されるので、
防水性能・保温性・足裏のクッション性なども余裕があれば考慮してもいいです。
丈夫で足をしっかり守るクローズドタイプ
開放サンダル・スリッポンではなく、つま先・かかとが保護されていて、脱げにくい靴が良いです。
また、「裸足・長靴(ラバーブーツ)では避難には向かない」
滑りにくい底(グリップ力)
雨・ぬかるみ・瓦礫(がれき)などを想定すると、底が滑りにくいものが安心。
キッズの靴選びでも「滑り止めソール」を推奨します。
脱ぎ履きが速くできる(ひもよりマジックテープなど)
園児だと慌てた時にひもを結び直すのが難しいので、
ベルクロ(マジックテープ)やゴム/ワンタッチで履けるタイプがベター。
足に合ったフィット感&脱げない設計
フィットしてないと走る・逃げるときに脱げやすいですし、
ずれると転倒リスクも。
足のサイズに合ったものを選びましょう。
さらに、「夜間・暗所の視認性を上げる反射材付き」などがあれば+αで安心。
非常時にすぐ履けるよう準備しておく
避難時には「靴を探す/履き替える」時間がないこともあります。
普段からその靴を履くか、すぐ出せる場所に置いておくことがベスト。
私のおすすめ「最優先仕様」
もし僕が園児の靴を避難用に選ぶなら、以下を最優先にします。
- マジックテープ/ベルクロ仕様(脱ぎ履き早く)
- 反射材付き/視認性が高いカラー(暗所・雨天も想定)
- 滑り止めソール+頑丈な作り(路面・瓦礫・ぬかるみ等)
- 普段使いもできるタイプ(慣れている靴が安心)
- 避難動作を想定してすぐ履ける場所に置く(夜中・地震直後など)
園児の避難靴 ― 運用面のポイント
①「普段履き=避難靴」にしておくのが基本
- 災害はいつ起きるか分からないので、普段から避難に適した靴を履いておくのが理想。
- 普段履き「安全な靴」なら、いざというときも慌てずに逃げられます。
- 園での活動にも向く「軽量・マジックテープ式・滑りにくい」靴を選びましょう。
② 予備靴を「避難靴」として保管しておく方法
- 園によっては、「非常持ち出し袋」や「避難靴袋」を個人で用意しておく運用もあります。
- その場合は以下のようにすると良いです。
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 保管場所 | 教室・玄関近く・個人ロッカー(すぐ履ける場所) |
| 収納方法 | メッシュ袋 or 通気性のある巾着袋 |
| 靴の種類 | 普段より0.5cm余裕のあるスニーカー(成長対応) |
| 付属品 | 名前札・反射シールを付ける |
| 点検頻度 | 学期ごと(サイズ・劣化チェック) |
| 園側の工夫 | 災害訓練のときに一度履かせて慣らす |
③ 靴の「サイズ成長対応」も忘れずに
- 園児は成長が早いので、半年に1回はサイズ確認を。
- 「避難靴を用意したけど履けなかった」ケースは実際に多いです。
- 成長を見越して、普段0.5cm大きめ+厚め靴下でもOK。
④ 「園での統一ルール」をつくると安心
園全体で靴の基準を統一しておくと、避難時に混乱が少なくなります。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 靴の形状 | スニーカータイプのみ(サンダル・長靴禁止) |
| 留め方 | マジックテープ or ゴム |
| 色指定 | 明るめ(白・黄色・明るい青など)反射付き推奨 |
| 保管 | 玄関近くの個人袋に「避難靴」としてまとめる |
| 表示 | 名前+クラス+避難ルートシール(園が貼る) |
⑤ 災害訓練のときに「実際に履く」
- 靴の準備だけでなく、避難動作とセットで訓練することが大事です。
- 泥・砂利・濡れた地面でも滑らないかを実際に確認しておくと安心。
- 園児自身が「この靴を履いて逃げるんだ」と認識しておくのも心理的に重要です。
⑥ 家庭と園の連携
- 家では「夜間避難時」も考えて、ベッドのそばにスニーカーを常備しておくのがおすすめ。
- 園では、保護者に「避難靴の選び方・点検時期」をプリントで共有すると良いです。
By 防災ママプロジェクト
#被災体験 #ママの教訓 #子育てと防災 #避難所生活 #家族を守る準備#防災頭巾#避難用シューズ